
自身の身体を測定機に仕立て上げる職種
たばこのブレンダーは1日300本余りを試喫するといいます。しかも、その微妙な味を測定するために、かなり健康的な生活をしています。例えば、規則正しく生活するのはもちろんですが、深酒や寝不足は一切しないというルールを徹底している、とのこと。
たばこの「味」は、機械では測定できないのだ、とか。
舌に直接触れるものなら、塩分や糖度などを測定する機器を利用すれば、ある程度の「味」というものがわかります。それでも、「うま味」を測定するものはアミノ酸を測定する以外に方法がありません。もちろん、総合的な「味」を判定する機械となると、まったく存在しないのが実状です。
それなのに「煙の味」です。
直接、舌に感じることができないものを相手にしているだけに、やっかいな代物です。飲料や食品以上に味の判定が難しいのが、たばこという世界なのです。
だから、ブレンダーは自分自身が唯一の「測定機」と言えます。
私も若い時に、ある嗜好品メーカーの営業マンを1年ほど経験しました。
営業マンといえども、味の判定能力が必要です。自社商品の返品要請があれば、一口含んだだけで、製造年月日を前後1ケ月の誤差で判断できるまでに、自己訓練を積んだものです。
現在は製造年月日や賞味期限がパッケージに印刷されていますから、訓練等はいりません。でも、25年前の当時、そんなしゃれたことをするメーカーなど皆無でした。そんな時代だったのです。
転職先のメーカーではブランドマネジャー職でしたが、自分で味覚を判定できるという能力は大変便利でした。なぜなら、この会社は外資系だったので、海外工場の品質管理が日本ほど徹底しておらず、規格から外れる商品もよく見かけたからです。特に、水分含有量が規格を外れているかどうかは、自分の口に入れれば、水分測定機よりも断然に早く判定できましたし、主要なものなら、原材料の含有量や質までも自分の舌で判断できたのです。
口腔は人間の身体の中で最も敏感な部分の1つです。ですから、素人でもそれなりに訓練を積めば、比較的楽に測定機械の水準に達することができます。他の身体の部分ではそうはいきません。手で掴んだだけで水分測定機より早く、しかもコンマ・ゼロ%の精度で水分含有量がわかる職人芸などは、やはり何十年もの訓練と資質を持っていなければ、できる相談ではありません。
自分でやってみよう
工場等の製造現場に限らず、自分の身体や感覚を客観的な尺度測定機にすると、便利なことが多いのは確かです。
いや、正直にいえば、マーケティングに携わる人間として、自分の感覚を測定機として仕立て上げるのは必須といってもいいでしょう。
何に使うのか?
まず上げられるのは調査の仮説づくりです。
次に戦略体系の策定の際に利用できます。
今回は、紙面の関係で、調査仮説の側面について主にお話しをいたします。
感覚を測定機にすることのメリットの話しをする前に、仮説とは何か、を説明しましょう。
仮説とは、要するに「質問設計者の思い込み」です。砕けた言い方をすれば、「こういう質問をしたら、こういう答えが返ってくるのではないか」という「思い込み」です。
これがないと、質問に対する回答肢が準備できないと言い切っても構いません。
次に、一連の質問を一定のページ数に納めなければなりません。回答に3時間もかかるような膨大な質問数を載せてしまっては、誰も回答したがりません。よしんば、回答をしようとしても、途中でイヤになってしまいます。
だから、
「こういう質問をしたら、こういう答えが多いだろう。だから、この答えは質問票のスペースの関係で削除しても、これは残しておきたい」
という検討が必ず必要になります。
質問設計者の思い込み、つまり、仮説は質問設計には絶対条件となるのです。
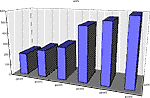 ところが、皮肉なことに調査というものは、「とにかくアンケートの質問を作って、丸をつけてもらえば」まがりなりにも数字という結果が出ます。
ところが、皮肉なことに調査というものは、「とにかくアンケートの質問を作って、丸をつけてもらえば」まがりなりにも数字という結果が出ます。
グラフにして、それらしきコメントをつければ報告書ができあがります。
ただ、幾ら立派なカラフルでわかりやすいグラフができたからと言って、実態を本当に表現しているのかどうかは別問題です。
女性の結婚観についての質問を例に上げてみましょう。
質問の設計者が男性の場合に良く見られるミスが、「時間軸を中心として質問を作成してしまう」ことです。例えば、「あなたは、いつ結婚したいですか。次の中から1つだけ○をつけてください」という質問に、
●1年くらいしたら結婚したい
●3年くらいには結婚したい
●5年後には結婚したい
●結婚したいとは思わない
という、回答肢を用意してしまいます。
ところが、若い女性に話を聞いてみると、「時間軸」による質問が意味をなさないのが大変良くわかります。
●仕事のめど(あきらめ)がついたら結婚したい
●結婚したい、と思えるような人と巡り会えたら結婚したい
●一度は結婚してみたい
●e.t.c.
という回答肢が本来の彼女たちの判断基準なのです。
もちろん、時間軸で結婚を考える人たちはいます。でもそれは20%に満たない少数派です。
仮説、しかも、正しい仮説がいかに重要なものか、おわかり頂けたでしょうか。
もしこの例のように、間違った仮説によって質問が作られたら、どうなるか。
前者の質問に出会った女性回答者は、回答肢と自分の感覚との違いに戸惑います。つまり、「○をどこにつけて良いのか、わからない」状態になります。そこで、自分の感覚に一番近いものに○をつけようと努力することになります。
「一度は結婚してみたいなぁ。でも、いつになるか、わからないし・・・結婚にそんなにこだわっていないし…いいや、時間が書いてない『結婚したいとは思わない』に丸をつけちゃえ」
かくして、「結婚したいとは思わない」、つまり、「結婚したくない症候群」が紙の上で大量に発生し、メディアに掲載されることになる…。そして、テレビで報道され、ドラマが作られ、一大ブームになってしまう。でも、実態ではないから、ブームが去ると「結婚したい症候群」が目立つようになって、それがブームとなり…
政府統計や金融機関のように公報活動の一環として調査を実施している企業では、これで良いのでしょう。調査結果が正しかろうが、間違っていようが、そんな数字を無視して企業活動方針を作るのですから。
でも、大半の民間企業は調査結果を元に様々な意思決定をしなければなりません。中には、調査結果によって、100億円単位の設備投資の判断を迫られることもあります。
「とにかくアンケートの質問を作って、丸をつけてもらえば」式の調査票で作った、華麗な表やグラフで一杯の調査報告書を信じて行動するには、余りにもリスクが大きすぎます。しかも、担当者の人事考課付きです。戦略や方針が失敗すれば、自分に対する人事評価も下がってしまう。実に身近な恐怖が襲ってきます。
調査の設計には正しい仮説が欠かせないのです。
仮説の誤解
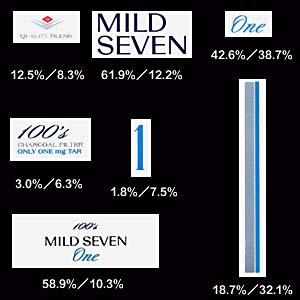 仮説に対する、良くある誤解は「問題解決型は事前の仮説が重要だが、発見型には仮説は不要」というものです。
仮説に対する、良くある誤解は「問題解決型は事前の仮説が重要だが、発見型には仮説は不要」というものです。
ここで、用語を知らない方への解説を簡単に付け加えておきます。
調査には問題発見型と問題解決型があります。
問題発見型調査とは、市場や消費者の全体の動きを探って、問題はないかを探索するものです。
例えば、パッケージデザインが気がついたら古くさいイメージになっていた、競合の商品の方がフケ・カユミが良く取れるよう品質改善をしていた等々です。
「問題」が見つかった場合、それを解消するための商品開発や、商品改善、広告などのコミュニケーション開発を見直すことになります。
年に1回など、定期的に調査を実施することによって、問題を発見しやすく、また、対処しやすくすることも多くの企業が採用しています。
一方、問題解決型は商品や広告などの案ができた段階で、それらのどの案がどう良いか、あるいは、どう悪いかを調べるものです。いわば確認のための調査です。
上の例で言えば、「今のデザインの特徴を保ちつつ、現代性のイメージを盛り込んだデザインを試作したが、どれが良いか。また、修正すべき点があるか」を確認する調査です。
問題解決型の場合、それぞれの案の「この点は自信があるが、ここの点はどうにも消費者の反応が読めない。だから、この点について、特に深く知りたい」などのニーズが最初にあります。既に仮説ができあがっている状態です。
ですから、「仮説が必要」というより、「仮説があるから、解決型の調査をする」のです。
一方、問題発見型は、一見、仮説は不要に見えます。とりあえず、質問を漫然と作れば、漫然とした回答が得られるからです。でも、上記の結婚観の例のような問題が起きることは、既に述べました。
戦略の場合も同じことが言えますが、詳しくは別の機会に譲ります。
データだけで構築したマーケティングは失敗する
いずれにしても、仮説なきマーケティング、いや、皮膚感覚なきマーケティングが成功する確率は極めて少ないと言えます。
データはあくまでもデータです。
私のように大量のデータに長年接していると、データの持つ限界がはっきりと見えてきます。その最大のものは、「データは一見客観的に見えて、実は極めて設計者・分析者による主観的なものだ」、という動かし難い現実です。
設計者・分析者が1人で勝手に想像した内容が客観性にまったく欠けるのは、誰でも容易に想像がつきます。
だからといって、多数の平均値であるデータに客観性があり、実態を正確に表現しているかというと「そうとも言えない」のも皮肉ながら事実です。世の中の事象は、片一方が誤っていたからといって、もう一方が正しいという単純な構造ではありません。
確かに、良く言われるように、1人で勝手に想像した内容と、数百人のデータとは、後者の方が信頼性が高いのは事実です。統計学的な真実です。
でも、そもそも、それ以前の問題として、分析する人間、質問を考える人間によって、データの結果は簡単に変わってしまいます。先ほどの結婚観はその格好の例です。
皮膚感覚、身体測定機としての感覚があれば、時間軸による結婚観の回答肢はおかしい、と簡単に気がつきます。でも、それがないと…
調査とは恐いものです。
その間違いを、簡単に防ぐには、皮膚感覚を使うのが一番なのです。
皮膚感覚と論理の使い分け – シストラットの場合
「シストラット調査の十ケ条」第5条「データで積み上げたマーケティングは失敗する」は、まさに本稿で解説した事柄を差しています。
では、皮膚感覚と論理をどう使い分けるのか。
私の場合、コンセプトにしろ戦略にしろ、まず「落ちる」つまり、ピンとくるまで自分をイジメます。この段階では理論などの表層的な意識や尺度は利用しません。
そして、「落ちた」時に、調査データや様々なマーケティング理論、心理学の理論でその正しさを検証するのです。
たまに、検証段階で自分の「落ちた」戦略やコンセプトの流れに矛盾が生じることがあります。その時は私の「落ちた」のは間違い、勘違いです。だから、もう一度、自分をイジメる作業に戻ります。
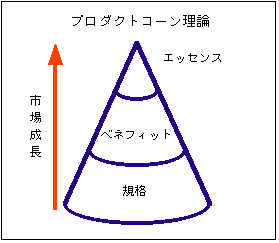 この一連のシミュレーションを繰り返すことで、戦略提案の内容が見えてきます。決して、シストラットのホームページにあるような理論をトントンと組み立てて報告書を作っているのではないのです。
この一連のシミュレーションを繰り返すことで、戦略提案の内容が見えてきます。決して、シストラットのホームページにあるような理論をトントンと組み立てて報告書を作っているのではないのです。
このプロセスは企画マンと類似していることに気がつく読者もいるかも知れません。
彼らも、自分をイジメて、「落ちる」までシミュレーションを繰り返します(「神が降りた」という表現を使う人もいます)。ただ、そこで使う検証は理論でもデータでもありません。自分の感覚を検証の道具として使用します。つまり、感覚を感覚で検証するというプロセスです。それだけに、良い企画マンはコンサルタント以上に感覚を常に鋭敏にしておく努力を怠りません。
コンサルタントと企画マンの最大の違いは事前データと検証理論です。
決定打だと言い切っても良いでしょう。
マーケティング・コンサルタントと自ら名乗っている西川りゅうじん氏や、木村和久氏は元々ポパイなど雑誌の編集者です。彼らは確かに、流行を敏感にかぎとり、それを応用する技にたけています。私には到底真似ができない嗅覚です。でも事前データや検証理論を駆使しているわけではありません。
誤解の無いようにつけ加えておくと、彼らと私とは活動分野が違うので、敵対心などはまったくありません。唯一困るのは、彼らと一緒にされることがあるということだけです。

