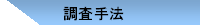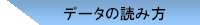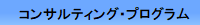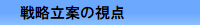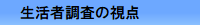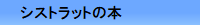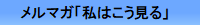商品・企業の差別優位性チェックポイント
DCCM理論 (TM)
ベネフィットの限界-商品の差別優位性
いくら理想的なベネフィットを見つけても、すでに市場で同様の商品を販売していたなら、意味がなくなってしまう。また、逆に言えば、同様のベネフィットを持つ商品が市場に存在する場合、対抗商品を上回る投資をすれば、シェアを奪うことも可能ということになる。
サントリーが圧倒的な宣伝費をかけて類似商品を頻発し、ニッカを潰したことがあった。このようにベネフィットが同じ場合、幅広い流通網や多額の投資は、競争を有利に導く。しかしこのやり方では投資効率は低下する。さらに流通力のない企業は、このやり方を踏襲できない。
そのため大半の企業は勝ち目のない競争に挑まねばならなくなってしまう。
DCCM理論は、こうした「力の論理」を補うためのものである。
差別性は情報カオス時代を生き抜くための自衛手段
DCCMとは、コミュニケーションを効率的、効果的に行うために必要な要素の総称である。
DCCMのDは「差別性=Differentiatiing」のDである。
差別性が商品や広告において重要な要素であることは、いうまでもないだろう。
社会心理学者のミルグラムは、情報が多すぎて処理できなくなったときに、人間は四つの行動をとると説いた。すなわち
(1)刺激に対する時間の短縮
会社の受付が、必要最小限の会話で客と対話しようとすることなどが挙げられる。
(2)重要でない刺激は無視する
空腹の時に、レストランなどの看板は目につくが、その他の看板はほとんど目に入らないという心理状態。
(3)責任を他人に転嫁する
街で人にぶつかっても相手が悪い、人が倒れていても自分には助ける義務はないとする心理状態。
(4)(相手に直接接触せず)社会的な仲介機関を利用する
隣人とのトラブルを家主や弁護士に訴えることなどが挙げられる。
現代の日本において、情報がきわめて過密になっているのは、今さら指摘するまでもないことだ。一説によると、情報供給量は10年前のおよそ2倍に達し、個人の情報消化もやはり2倍に増えているという。ミルグラムが指摘した4つの行動は、現在の日本、とりわけ首都圏の生活者に当てはまると考えていいだろう。
さて、ミルグラムは社会心理学の立場から、一般社会における人間の行動を説明したが、まったく同じ行動が消費市場においても観察できる。とりわけマーケティングにおいて重要なのは、(1)と(2)の行動である。ミルグラムは、商品や広告が氾濫する現代消費社会において、生活者は固有の情報(特定ブランドの情報)を収集する時間をできる限り短縮しようとし、そのため重要でないと思われる情報は、極力無視する傾向があると主張している。
ミルグラムのいう「商品や広告が氾濫する」典型的な場所はスーパーマーケットであろう。
スーパーでは少ないところでも25,000点、多いところでは40,000点もの商品を扱っており、それらすべてに目を配るのは容易なことではない。生活者が、スーパーマーケットで、一つの商品をたった0.4秒しか注目しないという調査結果もあるほどだ。また生理学的にも、人間がある物体の存在を認知するために要する時間は0.2秒で、その物体にどう対処するかを判断する最低時間は0.2秒だといわれており、ミルグラムの主張を裏づけている。
生活者が「重要でない刺激を無視する」のは、さまざまなブランドがひしめき合っている市場において、いつも自分が買っているブランド以外は、そのブランドに満足している限りにおいて「重要でない」刺激だからである。また同じような刺激、つまり商品の特長やメッセージが続いた場合、その刺激に対して鈍感になるのが情報社会の人間の生きる術だからでもある。
DCCM理論で差別性を最初に位置づけているのは、まさにこのためである。無視されたり鈍感になったりしたのでは、商品機能やメッセージに生活者が触れるチャンスすらない。ゆえに「差別性」で目を引き、まず生活者に商品を注目してもらおうという「商品の自衛手段」が必須になるのである。
差別性と優位性は違う
一つ注意しなければならないのは、「差別性」は、後に説明する「優位性」とは別の、独立した概念であることだ。
差別性とは、単に「違う」ことを意味するに過ぎない。「違う」だけでは、良い、悪い、好き、嫌いを判断できない。たとえばある商品が他の商品と「違って」おり、しかもそれが「気に入らない」商品であったら、それは「差別性があっても優位性がない」商品なのである。
別の機会で詳しく述べるが、つい数年前まで、時代の流れは「差別化商品」を求めていた。単なるもの珍しい商品が続々と発売され、もてはやされた。基本的欲求、雷同の欲求、優越の欲求を満たした生活者が、今度は他人と異なる行動をする、あるいは他人を否定することによってアイデンティティを確立しようとしたからである。
では「差別化の欲求」は、どのような行動となって表れたか?
たとえば男性を否定することで女性としてのアイデンティティを確立しようとしたり、60年代に行われたアメリカの黒人運動の"Black is beautiful"運動のように、自分だけが持つ特有のものに焦点を当てることによって自己確認をするなどの行動となって表れた。また生活者はこぞって他人と違うモノを求め、「差別化の欲求」を満たそうとした。
「差別性」が、即「優位性」としてもてはやされたのは、生活者が自己のアイデンティティを獲得しようとしたからだといえよう。もっともこれらの心理は、自己確認が終わった時点で忘れ去られる。現在、人と違うことが価値を持たなくなったのは、生活者がとりあえず、商品を選ぶことによる自己確認をし終えたからだといえるだろう。
差別性のみのキワモノ商品は真のヒットにはなり得ない
DCCMの第2の要素は「優位性=Copmpetitive」である。
ある商品に優位な点がなければ、購入行動が起こらないのは当然のことだが、「優位性」の対象になるのは、商品に直接関係する「機能」や「コンセプト」だけとは限らない。たとえば「どこでも買える」ことや「みんなが使っている」というのも、「優位性」になり得る。
さて、80年代の日本の生活者は、自分の価値観を模索し、それに合った商品を求めた。
「より差別的」であることが、同時に「優位性」でもあったのである。そのため、「差別性」さえ実現できれば、「優位性」は自動的に確保できた。しかし、先ほど述べたとおり、「差別性が高い商品」がそのまま「生活者の価値観に合致した商品」である時代は終わった。そこで「優位性」が再び独立宣言したのである。
「優位性」は、時代やターゲットが変わっやも、常に商品に求め続けられる要素だ。「差別化の時代」においてさえも、「優位性」のない商品は、実はたいして売れていなかったのである。
「差別性」を全面に出した商品は、日産の「Be−1」にしてもアイスクリームの「ホブソンズ」にしても、一時的に話題になってヒットはしたものの、トータルの売上は企業の業蹟のほんの一部に過ぎなかったり、人気があったのは数カ月であったりと、とても莫大な利益を生むようなものではなかった。異に「売れた」と断言できる大塚製築の「ポカリスエット」やアサヒビールの「スーパードライ」などの骨のあるヒット商品の足元にもおよばなかったのである。
つけ加えておくと、優位性と差別性が混同されているのは、生活者の欲求の移り変わりのせいだけではない。企業が本来優位性のないものをあると誤解しているケースも多いし、メディアに取り上げられた小さな成功例が、ヒット商品に祭り上げられてしまう場合も多々ある。
ヒット商品に学び、それを「見習う」際には、本当にそれがヒット商品と呼べるのか、単なる差別性しかない商品が、あたかも優位性をあわせ持っているように見えているだけではないか、を丹念に検討しなければならない。
説得性で生活者の疑いを晴らす
DCCMの第3の要素は「説得性Convincing」である。
さて、説得力を高める要素として、まず商品の素材や製法が挙げられる。
さらに、すでにブランドや企業に対する信頼が確立されている場合は、それだけで十分説得力を持ってしまうことがある。
たとえばアサヒビールが91年元日の全面広告で「今年、アサヒ、動く」というヘッドコピーで、新製品のティザー広告(発売前広告)を掲載した。当時はまだ「スーパードライ」の大躍進の輝かしい実績が人々の頭に残っていたので、「アサヒならやりかねないな」という期待を抱かせるに十分なメッセージだった。同様の広告をサッポロが出したなら、こうはいかなかっただろう。ちなみにこの新製品は、大矢敗した「Z」であった。結果的に、広告の説得力とはまったく違った商品となってしまったのは、皮肉なことである。
ブランドや企業そのものが説得力を十分に持っていない場合、最も効果がある材料は「事実」である。特に最近は、事実が持つ「説得性」に着目した広告が多くなっている。
たとえばJR東日本では、踏切事故の記録映像を放映して、事故防止キャンペーンを繰り広げた。また骨髄バンクの広告は、二一歳の若さで白血病のために亡くなった女性をメインキャラクターにして、大きな反響を呼んだ。これらは事実をベースにしたメッセージの強みを証明している。
さらにデザインも、「説得性」を高める要素になる。たとえば飲料の場合、ラベルを見て一目で味が想像できるデザインは、「説得性」を増す場合がある。
さて、「説得性」を別の観点から見てみよう。
心理学では、人間にはメリットばかり強調した方が信用するタイプと、デメリットについても多少触れておかなければ納得しないタイプがあるという研究結果が発表されている。この学説は「片面提示」と「両面提示」と呼ばれている。前者は、比較的低学歴で他人に依存する傾向があり、一方後者は、高学歴で自立心の高いタイプが多いという。実際、セールスマンの多くは、専業主婦に対してはプラス面を強調したほうが楽に売れるが、ビジネスマンにはマイナス面を若干見せながら説得した方がよいことを経験的に知っている。ただ、現在の生活者は、圧倒的に後者が多くなったといえるだろう。というのも、大卒のパーセンテージが上昇し、情報の操作にも長け、経済的、精神的にも自立した生活者が増えているからだ。しかもモノがあふれ、商品に関する生活者の知識も昔と比較にならぬほど豊富だからである。
マイナス面を素直に伝えたことが、功を奏した例を挙げてみよう。ある外資系の食品会社が1989年からテストマーケティングしていたスパゲティ・ソース「ドルミオ」は、ラベルに「フタを開けたら三日間でダメになってしまうので、使い切ってください」と書いた。これがかえって「ドルミオ」の新鮮さを訴求することになり、発売一カ月でシェアの30%を獲得したというものである。
従来のように「これがいいのだから、さあ、買いなさい」式の売り方では「説得性」が得られなくなってきている。商品にも広告にも、「これは、こんな理由でいいのだから、買いなさい」という理路整然とした説得力のあるメッセージが必要なのである。
市場ボリュームのチェック
DCCMの第4の要素は「市場性=Marketability」である。
下図を見てもわかるように、「差別性」「優位性」「説得性」は心理学からのアプローチ、つまり商品や広告のメッセージが個人に効率よく到達するよう編み出された手法である。
しかし同時に、商品も広告も同一のメッセージで大量の生活者に訴求しなければならない。
「市場性」とは、「差別性」、「優位性」、「説得性」を満たした商品が、どの程度の生活者に受け入れられるのかチェックするための要素である。
差別化の時代、企業はこの市場性を軽視して失敗したことが多かった。たとえば青山や六本木などのごくわずかな先端的な層にしか受け入れられないものを市場に投入したものの、売上がいっこうに上がらなかったケースなどである。これは、「市場性」を見極めなかったために起こった悲劇である。
DCCMの定義とは
DCCM理論は、商品コンセプト開発や、広告メッセージを開発するにあたって考慮しなければならない基本価値基準である。
ここでDCCMについてまとめてみよう。
| 差別性 (Differentiating) |
その商品が持っている他商品との違い。 |
|---|---|
| 優位性 (Competitive) |
(他商品と違う、同じにかかわらず)、「他商品より良い」、あるいは「他商品より有用な」ところ。 |
| 説得性 (Convincing) |
(差別性、優位性をサポートする)客観的で説得力のある事実やイメージ。 |
| 市場性(Marketability) | (上記3点を備えて市場に投入したときの)生活者の受入れ状況。 |
【注】このパートは「シンプルマーケティング」(翔泳社)から抜粋しました

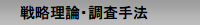
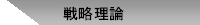
 プロダクトコーン理論
プロダクトコーン理論