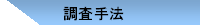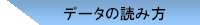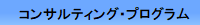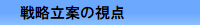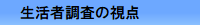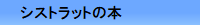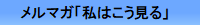商品・企業の性格をはっきりさせ、次の一手を読む
プロダクトコーン理論 (TM)
ひとりよがりだった企業の商品定義
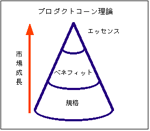 企業がマーケティング活動を行う場合、まず商品の「性格」を定義する必要がある。商品の定義の方法は、試行錯誤を重ねながら時代とともに変遷してきた。まずは、どのように移り変わってきたのか、そして現在、商品はどのように定義されているかを説明しよう。
企業がマーケティング活動を行う場合、まず商品の「性格」を定義する必要がある。商品の定義の方法は、試行錯誤を重ねながら時代とともに変遷してきた。まずは、どのように移り変わってきたのか、そして現在、商品はどのように定義されているかを説明しよう。
マーケティングという観念が日本に導入されたのは、昭和30年代初期である。
当時は、企業といえば大半が第二次産業だった。この時代の商品の定義は、おもに製造部門のためのものだった。すなわち「サイズは○○センチ」「重さは○○キロ」といった具合である。こうした定義は「規格」と呼ばれている。つまり規格とは、企業側の商品の定義である。当時は技術レベルも現在とは比較にならぬほど未熟で、企業も小所帯だった。そのため社員が各自の努力で商品知識をストックすることができた。しかも、市場や生活者からの発想があまり必要ない時代だったため、「規格」だけの表現でも、企業活動が可能だったのである。
ところが60年代になると、日本は高度成長期を迎えた。GDP成長率は二ケタの伸びを記録し、70年代になると消費が増大した。そして、市場や生活者からの発想を無視しては、モノが売れない時代がやって来た。さらに企業形態は広告部門、販売部門、営業部門、商品開発部門などに分化・専門化し、大規模になった。そのため製造技術をはじめとするハードウェアの知識で定義された商品規格では、業務が円滑に進まなくなった。極端に言えば、たとえばパソコンの世界では、ネットワーク環境が云々などと言われても、普通のコピーライターでは手に負えず、業務効率が低下してしまうという弊害が出始めた。つまり、専門知識を持った、専任のコピーライターが必要になり、当然その分、コストがかかるようになったのである。
そこでアメリカの広告代理店によって開発された「コンセプト」という概念が採用された。
「コンセプト」は「規格」と異なり、基本的に技術用語を使用しない。生活者が使用するわかりやすい言葉で商品を定義しようというのが、「コンセプト」の特徴だった。
ものぐさになった生活者
「コンセプ卜」が浸透してからしばらくは、生活者は「コンセプト」を手がかりに、商品の購入を決定していた。「これは○○という商品です」という企業からのメッセージを受けると、生活者は「それなら、この商品は自分にとっては△△なんだ」と翻訳したうえで、商品を買うか買わないかを決めていた。
ところが70年代後半から、企業はこぞって市場を細分化して、新製品を乱発した。しかし、そうそう新製品をつくれるはずもなく、パッケージやネーミングを変えただけの安易なリニューアル商品が横行した。生活者は「新製品」という言葉に踊らされてモノを購入したものの、そのたびに失望するばかりだった。そこで生活者は「買わない」という非常手段に訴え始めた。
生活者はなぜモノを買わなくなったのか?
第一に、いちいち面倒な翻訳作業をしなければならないような商品は、相手にする必要はないと開き直ったからである。
第二に興味のない分野についてはできるだけエネルギーを省いて、労力を興味のある分野に集中しようと考えたからだ。
生活者はますます賢くしたたかになっていったのだ。
こうして「コンセプト」は限界をさらけだした。
では、なぜコンセプトは行き詰まったのか?
「コンセプト」とは、元来、モノづくりに携わるスタッフが、共通の言語で理解できるよう開発された言葉である。その言葉が生活者にもわかりやすかったので、広く普及したのである。
つまり、そもそも誕生した経緯からして、基本的に生活者の存在は考慮されていなかった。にもかかわらず、コンセプトに、ターゲットや目標など、あらゆるマーケティング要素を詰めこむことが流行ってしまった。よく見かけるのは、次のような記述である。
「商品Aは、都会を自由に闊歩する若年女性のためのリラクゼーション・アイテムである」
「商品Bは、味とコクを求める生活者のためのチーズである」
「商品Cは、業界トップの売上を目ざす、新しいタイプのデザートである」
こうした記述では、製品コンセプト(=生い立ち)とターゲットが混乱されてしまっている。
商品Bにいたっては、ターゲットの設定すら、まともにできていない。チーズに「味とコク」を求める層は確かに存在するだろうが、それはどんな人々なのかがまったく描かれていない。
本来ターゲット設定とは、開発やマーケティング及びセールス業務に携わるスタッフ、さらに製品や広告を通してメッセージを伝えるべき生活者に対して、「この商品はこういう人たちのために作ったモノです」と知らせるために行う作業のはずである。ターゲットの記述を見て、広告部門は作るべきCMの素材を考える。また製造部門はスペックや設計の細部を検討する。
そして生活者は「自分のために作られた商品か否か」を判断する。
A、B、Cのような、ターゲット設定ともコンセプト設計ともいえない中途半端な規格では、本来の役割がまったく機能しなくなる。そしてそれは即、各部門がターゲットをバラバラに解釈して、チグハグなマーケティング戦略を行うことを意味する。
今までのところをまとめてみよう。
コンセプトは、マーケティングやセールスの専門家を、技術者にしか通用しない専門用語、あるいは数値の塊のような製品の定義から開放したという点では、功績は大である。しかしその生い立ちゆえに、生活者の視点が抜けてしまった。これに対して、生活者は面倒な翻訳作業を拒否し、自分に興味のない分野は無視することにした。
さらにコンセプトは、あまりにもわかりやすい言葉づかいゆえに、マーティングの他の要素を安易に盛り込まれてしまった。そのため、商品の中核ともいうべき定義がぼやけてしまい、本来の目的にかなわないものに退化させられてしまった。これがコンセプ卜の現状である。
これから説明するプロダクト・コーン理論は、あくまでも製品戦略がベースになっている。
プロダクト・コーンによって定義されたそれぞれの要素が、本当に生活者に受容されるものであることがわかれば、製品改良の方向もすぐに見えてくる。当然、「競合商品が何であるか」「それらが動きを見せたときにどんな手を打つべきか」という戦略レベルの思考も明確になるのである。
さらにもっとも重要なことは、製品レベルで主張したいことを規格に凝縮して切り離すことにより、「生活者がその商品を買う深い動機」を探ることに集中できるという点だ。これに成功すれば、コンセプトという一つの要素に、ごった煮的に少しずつマーケティング・エッセンスを放り込んで、製品概要が完成したような気になる愚を犯さずにすむのである。
商品の性質をはっきりさせるプロダクト・コーン理論
先ほど、生活者が商品のコンセプトを翻訳することに疲れ、モノを買わなくなったと説明した。
それでは、コンセプトを追うのに疲れた生活者はどうしたか?
「商品が何かはわかった。だからそれが私にとってどんな得になるか教えて!」と、企業に翻訳作業の肩代わりを求めたのである。
そこで普及の兆しを見せ始めたのがベネフィットである。ではベネフィットとは何か?
ベネフィットとは、生活者が得するコト、モノである。
たとえば高性能のパソコンがあったとする。商品名は「Monarch XG-e」。この商品の特徴は「CPUにインテル Core i7-3930K、NVIDIA GeForce GTX680 2GB、インテル X79 Express チップセットのマザーボードを搭載」だが、こういったところで一般の人には何のことだかさっぱりわからない。では、生活者はこのパソコンをなぜ欲しがるのか?生活者は単なる鉄の塊が欲しくてパソコンを買うのではない「Monarch XG-e」は、通常のパソコンより2〜3倍も作業が速くなる。ゆえにこのパソコンを購入すれば、たとえば仕事の時間を短縮できる、その間に別の仕事をこなせる、そして遊ぶ時間が増えるのである。これがベネフィット(得するコト、モノ)だ。いわば生活者は遊ぶ時間を買っている、あるいは仕事の時間を短縮してイライラを解消する手段を買っているのである。
しかし、ベネフィットは単独では商品の性質を決めることはできない。商品には、ハードを定義する部分も必要だ。また、イメージも規定しておかなければならない。さもないと、実際の商品開発やコミュニケーション戦略を行う過程で、スタッフの意思統一ができないからである。また、作り手の意志がバラバラだと、生活者も商品をどのように理解したらいいのかわからない。その結果「買いたい」という気持ちが起こらない。
要するに、ベネフィットや規格を盛りこんだ総合的な商品定義が必要になるわけだ。
この概念がプロダクト・コーン理論である。
では、プロダクト・コーン理論はどんな定義で構成されるのか?下図を見てほしい。
規格=企業側の商品定義
ベネフィット=生活者の得するコト、モノ
エッセンス=商品が持つ性格(擬人化)
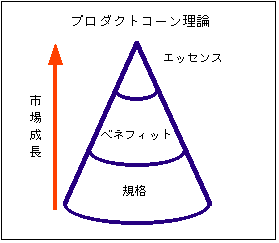
以上の三つでプロダクト・コーンは構成される。これを、人間を例にとって説明してみよう。
たとえばAさんという人がいたとする。
Aさんは東大出身で、身長180センチ、品のある整った容姿でちょっとやせ型。外務省に勤めている29歳で、成城学園の閑静な住宅街の一軒家に住んでいる。
いま挙げたAさんの特徴はすべて「規格」だが、このままでは、Aさんの人となりは、おぼろげにわかるだけだ。こうした特徴だけではAさんはいかにもステレオタイプで面白みのない人間になってしまう。そこでAさんの「エッセンス」が登場する。
Aさんは優しい。何事にも気配りを忘れず、バランスのとれた性格だ。ちょつとクールで理性的だ。腎い。Aさんは女性に手が早い。これが、Aさんのエッセンスである。
では、Aさんの「ベネフィット」は何か?
Aさんと一緒にいれば、人に自慢できて自分の上昇志向を満たしてくれるかもしれない。知らないことをいろいろ教えてもらえるかもしれない。また結婚すれば、Aさんの自宅に住めるので、家賃が浮いてお金がたまるかもしれない。これらはすべて、Aさんの「ベネフィット」だ。こうした多面的な説明によって、Aさんの人格が浮き彫りになり、人々の記憶に残りやすくなる。
モノの特徴を述べる際にも、まず、機能や商品の定義を説明する。次に、その商品を買うと何が得かを説明する。最後に商品のイメージを擬人化して述べてやると、きわめて人の記憶に残りやすいのである。Aさんの例では、日本人の本音と建前を考慮して、あえて「ベネフィット」を最後に紹介したが、これはあくまで例外である。
プロダクト・コーンは、人の記憶にとどまりやすいもっとも効率のいいシステムである。記憶の効率が良ければ、ムダな広告は必要なく、経費の削減になるわけである。
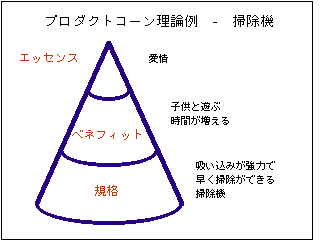
プロタクト・コーン理論の実例
具体例を挙げて説明しよう。
【プロダクト・コーン事例1】ビオレU毛穴すっきりパック
最近、ヒット商品を連発している花王だが、ビオレU毛穴すっきりパックも、その着眼点の鋭さで大ヒットとなった。
形状は単なるシートである。これを顔に貼り付けるだけで、毛穴に残った汚れがくっつき、シートをはぎ取るときに汚れもすっぽり抜ける仕組みである。
従って、規格は「鼻の毛穴をそうじするシート状の簡単パック」となる。
さて、この商品がヒットした最も大きな理由が、シート上に毛穴の汚れが粒状についているのを確認できる、という点だ。たばこのフィルターなどとまったく同じ心理効果である。たばこのタールが透明のフィルターに溜れば溜るほど汚らしいのだが、これが、今まで肺の中に入っていた、と考えると、ゾッとする。そして、その効果がはっきりすればするほど(商品が汚くなればなるほど)、機能が高く感じるのである。
従って、ビオレUのベネフィットは「気分がすっきりして、きれいになる(気がする)」である。
だから、イメージはあくまでも「すがすがしい」となる。
この商品の見事なところは、このベネフィットとエッセンスをそのままネーミングにしたことである。「パッケージは(テレビなどのマス媒体より)最大のコミュニケーションである」と言われるが、ビオレU毛穴すっきりパックは、まさにこのことを実践した好例である。商品の質もさることながら、これでヒットしないわけはない。
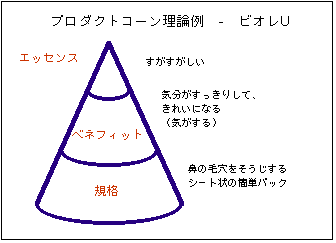
【プロダクト・コーン事例4】「レストラン・トップ」
最後に高層ビルの50階にある架空の店、オシャレなレストラン「レストラン・トップ」を検討しよう。「レストラン・トップ」の規格は「50階建てビルの最上階にあり、一流のシェフと一流の素材、美しい夜景が楽しめる」ことだ。
ベネフィットは「ねらった女性をおとせる」ことだ。
エッセンスは「誘惑」である。
規格→ベネフィット→エッセンスの流れを破壊せよ
通常、プロダクト・コーンの訴求要素は、規格→ベネフィット→エッセンスと移行する。商品・広告開発に際しては、その商品の市場や成長、競合状況などによって、プロダクト・コーンの何をメインにすればいいかが決まる。
では、全体的に今までは何を訴求した商品が成功していたのか?わかりやすい例として広告をみてみよう。
数年前までは、ベネフィットを訴求すると効果的な市場が多かった。ベネフィット戦略が成功した例として大塚製薬の「カロリーメイト」が挙げられる。1982年発売の「カロリーメイト」は、当初、「バランス栄養食」という規格を訴求して、コンスタントに年間220億円前後の売上をはじきだしていた。規格を訴求する戦略は十年間続けられたが、1992年、広告コピーを「朝カロリーメイト、昼カロリーメイト、夜は友人と会食。新しいダイエットの提案です」という趣旨に改めた。つまり、規格からベネフィットの訴求へと移行したのである。
この戦略が当たり、現在、売上を200億円超まで伸ばしている。
大半の企業は、規格からいきなりエッセンスに移行しがちだ。その結果、女性モデルがイメージキャラクターと称して、ニッコリ笑っただけの広告ができあがる。私が「ベネフィットが重要だ」と主張するのは、こうして感性マーケティングの罠にはまっているケースが実に多いからである。加えて、イメージ(エッセンス)中心の戦略を実施している業界では、実はベネフィットをメインにするよりも規格を核に戻した方が効果的なのである。その理由を実例を挙げて説明しよう。
たとえばビール業界は、「どういうわけかキリンです」という昭和45年のキリンビールの広告に代表されるような、イメージによるコミュニケーション戦略の時代が長期間(容器戦争時代を除いて)続いた。
この流れを壊したのが、アサヒビールである。
アサヒビールは、昭和61年の「コクがあるのにキレがある」と、翌年の「辛口、生」のコピーを発表して、ビール業界の広告サイクルを断ち切った。この広告がジャンプボードになり、当時サントリーと最下位を争っていたアサヒビールは一躍大舞台に躍り出て、とうとうキリンを抜いてトップ・メーカーの座を狙おうとしている。
アサヒビールの勝因は何か?イメージ広告が主流だった80年代において、いきなり規格を訴求したことである。「事実」が「慣習」を打ち破ったのである。
さらにビールと同じような現象が、たばこの世界でも起こり始めている。
従来のたばこの広告は、エッセンスを訴求したイメージ的なものが多かった。90〜91年後半までの「ラーク」のコピーは「これが世界のフレーバー、ラーク」だった。また「キャビン」のコピーは89年に「キャビン・スピリット」、92年に「赤いキャビン・ボックス新発売」、「感じるレッド。鮮烈デビュー」と、「感性マーケティング」を代表するような広告だった。
しかし最近のたばこのCMは、規格訴求タイプが成功している。たとえば「平均的なたばこよりタールを33%カッ卜」してデビューした「メリット」が成功したし、より最近の例でも、「ネクスト」が、タール1mg、ニコチン1mgという禁煙パイポのような商品を投入し、「一番軽くて、驚きのうまさ」というコピーで同水準の軽さの先行ブランド「フロンティア」に真っ向から攻撃を仕掛けた。そしてついに「フロンティア」の売上を抜いてしまった。
エッセンス(イメージ)は、慣習に似ている。ビールに関していえば、かつては「なぜキリンなのか」と聞く人もいないし、「なぜキリンなのか」を説明できる人もいなかった。しかし、ビールといえば「どういうわけか」キリンという常識がまかり通っていた。しかしこの流れに「規格」という名の「事実」を引っさげて、アサヒビールが登場し、躍進したのである。
【注】このパートは「シンプルマーケティング」(翔泳社)から抜粋して、加筆修正しました
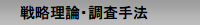
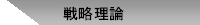
 プロダクトコーン理論
プロダクトコーン理論